私は研修関連の仕事に携わって25年が経過します。他のお仕事に携わっておられる方々と同じように、私も自分の仕事にプライドを持っています。
それゆえなのか、私が卑屈になっているのか、ふとした場面で「えっ?」と思うことがあります。

今回のブログでは、私のぼやきのような感じになるかもしれませんが、その点について書きます。
*************************
1.研修のプロ? それってどういう意味?
私は、他人に言われて「えっ?」と違和感を抱く言葉があります。その言葉は、
「研修のプロ」&「研修屋さん」
です。
なぜ「研修のプロ」とか「研修屋さん」と言われると違和感を抱くのかと言いますと、そういった発言をする人は、研修を「経営に資する手段」と見なしていないのではないかと思うからです。
違和感に加えて、残念さを感じるときがあります。それは、「研修のプロ」や「研修屋さん」という言葉を人事部門の方々から聞くときです。これまでに何度も聞いたことがあります。

ご本人がどういうつもりでおっしゃっているのか分かりませんが、なんだかとても寂しい気持ちになります。
経営に資さない研修は無価値です。研修を「経営に資する」ものにするためには、それに関わる人は色々と勉強せねばなりません。
例えば、クライアントである企業や組織、受講者のこと、仕事内容などに関して知らなければなりません。現状の問題を聴きだしたり、課題を整理したりするためには、リスニングやインタビューに関する知識やスキルだって必要です。
私が関わることの多い「人材育成」や「組織開発」に関するものであれば、その分野の専門知識やスキルが当然必要です。例えば、リーダーシップ、モチベーション(動機づけ)、チームワークなど。他にも、経営に資するために必要な専門知識を持っておく必要がありますし、受講者に伝える(or 学んでもらう)ことを自分が実践できなければ説得力も生まれませんので言行一致(=実践)も大切です。
更に、研修を企画・運営するのであれば、研修設計に関する知識、運営に有益なファシリテーションやインストラクションに関するスキルが必要です。
このように、様々な知識やスキル、継続的な経験学習を通して、「研修のプロ」ではなく、経営に資する(人材育成・組織開発の)プロフェッショナルとして、経営施策としての「研修」を企画・実施運営しているという自覚をもって仕事をしている人がいます。
ですので、「研修のプロ」や「研修屋さん」といった言葉を聞くと、研修に関連している人たちのことを
■クラス(研修をやっている空間)を上手に切り盛りできる人
■受講者から好かれる人/不満を抱かれない人
■受講者アンケートの結果(満足度評価)の良い人
くらいにしか見ていないのではないかと感じます。「研修屋さん」と言っている本人は無自覚かもしれませんけど。更に言えば、そういった言葉を口にする人は、研修を一過性のイベントとして見ているのではないかと・・・。

残念ながら、世の中の多くの研修が、経営にどう繋がっているのかが不明確ですし、1回きりのイベントになっていますので、「研修のプロ」や「研修屋さん」という呼称が出てくる状況もわからなくもありません。
※参考:「研修屋さん」という言葉が生まれてしまう理由を書いたブログへ

世の中にいらっしゃる、本当に ”プロフェッショナル” な人材コンサルタントや人事担当者の皆さんと共に、研修に対する見方を変えていくように、今後も頑張っていきます!
*************************
2.研修って、そんなに簡単にやれちゃうものですか?
もう1つ、「えっ?」と思うのが、雑な/テキトーな研修を企画・実施運営している人たちの存在です。当人はそんなつもりは毛頭ないのかもしれませんが、私にはそう見えるときがあります。
上記しましたが、研修って、簡単に誰でも気軽に企画・設計・運営できないと思っています。私の経験ですが、研修業界で1人前になるのに3~4年はかかりました。(私が無能、かつ他者や経験から学ばない性格であったことも影響していますが・・・)
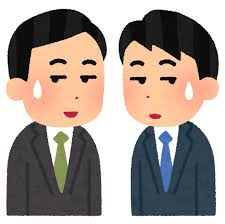
研修にまつわる基本的な知識やスキルを持っていないであろう、雑な/テキトーな研修を企画・実施運営する人たちって、こんな感じなのではないかと想像します。
■伝えたい/教えたい/理解してほしい/知ってほしいと思っている内容が、経営にどう繋がるかまで考えていない
■内容が面白そうだから/役立ちそうだから/目新しいからという理由で研修をやる
■研修を一度やれば、全員とは言わないが、人(の意識や行動)は変わると思っている
■研修後の成果にまで責任を感じていない
■話すことに自信がある/受講者を楽しませる自信がある
■その場が盛り上がれば/楽しければいいと思っている
私は、そんな人たちが企画・実施する研修は、経営にとってほぼ無価値だと想像しますし、忙しい従業員に時間をもらっているのに無責任・失礼ではないかを考えます。
そして、そんな雑な/テキトーな研修をやった結果として、研修に対して「面倒くさい」「意味がない」と思う人の数がどんどん増えているかもしれませんし、上記した「研修屋さん」と言う言葉が出てきてしまうのかもしれません。
当たり前のことですが、研修を企画・実施運営するのであれば、
■それが経営とどう繋がるのかを明確にする
■研修の成果はなにかを定義する
■意識や行動の変容にまでどうつなげるかを考え、全体設計する
■仮に、受講者にとってシビアな内容であっても、経営に必要なことならばやる
といったことが必要です。
大して価値のない研修にお金をかける・・・・・企画・運営側の自己満足になっていませんか?
雑な/テキトーな研修を企画・実施運営することを撲滅したいところです。

外部からであれ、内部からであれ、企業や組織への研修を企画・実施運営することで、経営に影響を与える立場にいるのであれば、プロフェッショナルとして必要な知識やスキル、マインドセットを有していたいものです。
*************************
最後に。
多くの会社で、人事制度の変更、コンプライアンスの遵守、ハラスメント防止、DEIの浸透など、経営にとって重要な施策を従業員に徹底するために、やたら多くの研修(e-learningを含む)が行われています。
ただ、その殆どの研修において、ほぼ学びになっていない形式的なイベントになっています。企画者は「研修を提供すれば、とりあえずOK」とでも思っているのでしょうか。これでは、研修に対する見方はますます軽いものになりますね。

今日は私のぼやき、または思い過ごしのようなことを書きました。皆さんはどのように捉えられましたか?(ご感想を伺いたいです)












